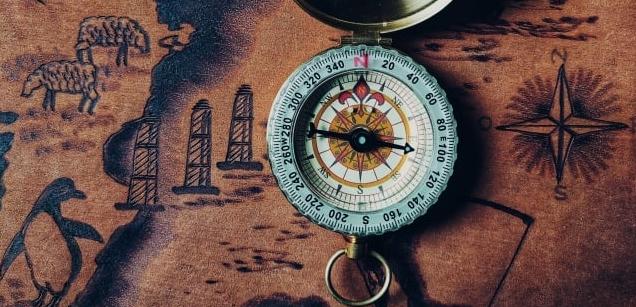
Business 遺言 |
最近、「遺言書(公正証書遺言) 」 を残すケースが増えてきました。 遺言書をつくっておけば、トラブルにならなかった事例がたくさんあります。 公正証書を作成し、相続人が無用なトラブルに巻き込まれないよう、早めに行動しましょう。 突然、無くなった時に故人を偲ぶことができないまま争いが始まるケースが少なくありません。 残された家族のためにも、「遺言書(公正証書遺言)」を残しておきましょう。 |
1. 遺言を書くことのメリットは何ですか ある方が死亡されると相続が開始され、法律で決められた相続人に、法律で決められた割合で相続されます。 しかし、それでは、亡くなった方が希望する人(団体)に、財産をあげることも出来ません。また、遺産分割協議や銀行・法務局などの相続の手続も結構面倒です。さらに、予想に反して、相続人間で揉めてしまうこともあります。 この様な場合に、亡くなった方の最後の意思を尊重して、生前に、ご自身の財産を処分することを認めるのが、遺言という制度です。 |
2. そもそも遺言は必要ですか。 (1)遺言がないとどうなりますか。 亡くなった方の財産は、基本的には法定相続分にしたがって分けることになります。 (2)法定相続分とは何ですか。 民法で決められた相続割合です。 例えば、亡くなった方に妻と子どもが2人いれば、妻2分の1 子ども4分の1 子ども4分の1 となります。 (3)法定相続分で分けることができるなら遺言はいらないのでは? 法定相続分で分けるだけでは不都合な場合が沢山あります。 例えば、妻の老後を考えて、妻にたくさん残したい場合などです。 |
3. 遺言を作るために必要なことは何ですか。 (1)誰でも遺言を作成することはできますか。 年齢15歳以上で、意思能力(遺言事項を具体的に決定し、その法律効果を弁識するのに必要な判断能力)が必要です。 (2)認知症の方でも遺言書を作成できますか。 できる場合があります。 認知症であるからといって、意思能力がないわけではありません。 認知症の方でも程度によって、意思能力(遺言事項を具体的に決定し、その法律効果を弁識するのに必要な判断能力) がある場合があります。 自分の財産をどう分けたいか、この遺言書を書いた場合、どうなるのか分かっていれば大丈夫です。 【認知症の方の場合】 意思能力があること証拠化しておく必要があります。 (医師の診察を受けて、遺言能力の有無の判断につき診断書を書いてもらう。) (動画を撮影し、財産分割方法の理由を話してもらう。) 公正証書遺言で作成しておけば、公証人が意思能力があるかチェックしてくれますし、証人が後にトラブルになった場合、証言してくれます。 また、簡単な内容にすることも必要でしょう。 詳しくお知りになりたい方は、ご相談下さい。 |
4. 遺言には種類がありますか。 遺言は、①自筆証書遺言、②秘密証書遺言、③公正証書遺言の3つの方式のいずれかによる必要があります。 ①の自筆証書遺言は、遺言者が全文を自分で手書きして、日付、氏名を自署して押印するだけです。ただし、遺産の一覧である「財産目録」についてはパソコン作成文書や資料で代用することができます。 一番手軽な方法ですが、誰にも知らせずに放っておくと、遺言書を誰も見つけてくれないおそれがありますが、法務局で保管してくれる制度を利用することも可能です。その場合、裁判所での「検認」の手続が不要になります。 自筆証書遺言は、法律専門家の関与がない場合、文章に不明確な点があるなどの理由で、遺言書が無効になったり、死亡後に訴訟になってしまうことがあります。せっかく書いたのに、もったいないです。 ②の秘密証書遺言は、遺言者が遺言書を作成し、封印した後に、証人2名とともに公証人の面前で自分の遺言書である旨等を申述して公証を得るものです。秘密が確保される一方で、内容について公証人が関与しないため、内容について争いになる可能性もありますし、紛失の可能性があることも①の自筆証書遺言と同様です。 そこで、一般的には③の公正証書遺言がお勧めです。公正証書遺言は、遺言の内容を公証人が公正証書によって作成するものですから、有効性が確保され、その謄本が公証役場に保管されるので、紛失することもありません。内容の確実性という観点からすれば、やはり②の公正証書遺言が安心といえるでしょう。 弁護士がお勧めするのは、問題が生じにくい公正証書遺言です。 |
5. 公正証書遺言の作成方法は? (弁護士に依頼する) 私たちは、法律の専門家として、ご本人の希望をよくお伺いし、その内容を正しく明確にした遺言書の案文を作成します。 内容が確定すれば、公正証書遺言を作成することをお勧めしています。 遺言公正証書を作成するために必要な証人は、弁護士や法律事務職員がなることもあります。 また、亡くなった後に、遺言をそのとおり実現する遺言執行者に、弁護士や弁護士法人を指定していただくこともあります。 (1)まず相続関係図を作成する。 相続人全員の戸籍謄本、住民票、除斥謄本など各種書類を収集する。弁護士が職権で調査します。 (2)次に相続財産目録を作成する。 弁護士が作成します。 (3) 遺言書の原案を作成する。 「誰にどのような財産をどのように相続させるのか」遺言者のお話を伺い、弁護士が作成します。 (4) 公証役場にてすべての手続きが終了します。 公証役場の予約を取り、遺言されるご本人と証人2人で公証役場にいき、証人立ち合いのもと、公証人に口頭で原案を告げて、公正証書にしてもらう。 弁護士が公証役場に予約をとって、手配します。ご相談ください。 |
6. 遺言書が必要な場合の一例 (法定相続分で分けるだけでは不都合な場合) (5)いわゆる熟年再婚の場合 (6)相続人が全くいない場合 |
(1) 夫婦間に子どもがいない場合 夫が亡くなると(このとき両親は既に死亡している。)、妻が全財産の4分の3、夫の兄弟姉妹が4分の1を相続することになりますが、夫の兄弟姉妹には遺留分はないので、生前、「妻に全財産を相続させる。」と遺言しておけば、妻は全財産を確実に相続することができます。 もし、遺言書がなければ、奥さんは、ご主人の兄弟の協力を得て遺産分割をしなければ、銀行で換金もできません。 |
(2) 自分を介護してくれている子と、してくれない子がいる場合 高齢の方を介護することは、大変な労力と精神力を要します。自分の死後、介護をしてくれた子と介護をしてくれなかった子との間で、遺産分割の争いが生じることがよくあります。遺言によって、介護をしてくれた子の寄与を考慮に入れて遺言しておくと、お子さん間の争いを防止することができます。 |
(3) 子の配偶者に財産を分与したい場合 子の配偶者は、相続人ではありません。 長男の妻に、老後の世話になっていたとしても、長男の妻には相続権はありません。 そこで、遺言によって、遺贈することができます。 もっとも、ここは相続法が改正されて、長男の妻であっても「特別寄与料」というお金を受け取ることができるようになりました。 特別寄与料が認められる親族の範囲は 「6親等以内の血族」 「3親等以内の姻族」 無償の療養看護などの労務提供を行い、それによって遺産が維持または増加したことが要件です。 特別寄与料の金額は、「寄与行為によって支払いを免れた金額」や「遺産が増加した金額」を基準に計算します。 しかし、特別寄与は、他の相続人とトラブルになる可能性があるので、確実に子の妻に財産を分けたいのであれば、遺言書を作成することをお勧めします。 |
(4) 先妻の子と後妻の子がいる場合 先妻の子と後妻の子はいずれも相続人になります。 交流がないため、連絡が取れなかったり、遺産分割で争いが生じやすいので、遺言によりきちんと遺産の分け方を決めておいた方が良いでしょう。 |
(5) いわゆる熟年再婚の場合 高齢の男性が妻と死別した後に、他の女性と再婚した場合、後妻も2分の1の相続権があります。 後妻と先妻の子ども達は、血のつながりがないので、遺産分割の際に争いが生じやすいです。 残された奥さんの老後の生活を守るためにも、遺言により遺産の分け方を決めておく必要があるでしょう。 |
(6) 相続人が全くいない場合 相続人が全くいない場合、遺産は原則として国庫に帰属します。 それを防ぐためには、お世話になった人やご自分が財産を渡したい人に遺言で遺贈する必要があります。 いつもお世話をしていただいている遠い親戚、知人などに、渡される方もいます。 |
(7) 同性のパートナーに遺産を残したい場合 同性のパートナーと夫婦同様の生活をしている場合、日本には同性の婚姻制度がないので、亡くなった場合、相続することができません。 相続するためには、パートナー間で養子縁組をするか、遺言書を作成するか、2つの方法が考えられます。 1つは、養子縁組をすることです。年長者が親、年少者が子になります。役所に届け出ることにより、養子縁組をすることができます。 なお、他に法定相続人がいる場合、全ての財産を相続させることが出来ないので、注意が必要です。 もう1つは、公正証書遺言を残すことです。遺言を残すことで、確実にパートナーに財産を残すことができます。 |
自筆の遺言書でよいのか、公正証書にすべきなのか、遺言書の形式についても、ご相談ください。 自筆の遺言書を既に作成されている場合、何か問題点はないか、チェックもさせていただきます。 遺言書さえあれば、こんな苦労をしなかったのに、と言われることが多々あります。 遺産分割調停を何年もやっている方がいらっしゃいます。 ご自分が亡くなったときに、大丈夫なのか、ご相談ください。 |



